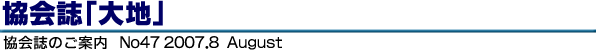|
旭ボーリング(株) 間舎 美幸 |
 |
|---|
29.北上幻想
岩手県の面積のほぼ3分の2を占める北上山地の西側を、縁取るように流れる北上川の名は、鎌倉幕府の事跡の史書である吾妻鏡の文治5年(西暦1189年)9月27日の項に「北上河」として初出し、“北上”は、この地方一帯の古称である“日高見(ひたかみ)”の転訛といわれる(「北上の歴史」より)。
『当地域社会は北上川、北上山地、あるいは北上平野と不可分であり、過去、現在、未来を通じ、山川「北上」は生活形態の根源をなす』として、その名を戴くここ北上市では、毎年8月上旬に「みちのく芸能祭り」が盛大に開催される。
この祭りの演目のひとつに鹿踊り(ししおどり)がある。鹿角を生やす被り物と装束に、ササラを背負い、太鼓を打ち鳴らしながらの群舞は、勇壮な中にも一抹の物悲しさが漂う。
現在は五穀豊穣、厄難払いの踊りとして伝承されるこの鹿踊りの起源は、鹿の魂の供養とも、春日大社への奉納踊りとも言われる。
真夏の深い青空の下、公園の緑の絨毯のような草地で、街中とは思えぬ静けさの中に響く単調だが力強い太鼓の音を聞きながら、ひたすらその動きを見つめていると、草陰から昔人が息を潜めて見守ったであろう鹿たちの跳梁跋扈する幻影を見てしまう。
その昔、文明の垢に塗れる前、まさに自然の一員であった古の人々は、鹿や熊を、風や雷を、恐れるとともに、それらと言葉を共有できたのではないだろうか。緑深い北上山地では、人間と自然とのこんなドラマが毎日繰り広げられていたことだろう。
岩手県の生んだ童話文学者・詩人の宮沢賢治は、その童話「鹿踊りのはじまり」で、人間と鹿との交歓の様子を描き、それを『ひとは自分と鹿との区別を忘れ、いっしょに踊ろうとさえしています。』(「『注文の多い料理店』新刊案内」より)と説明している。
ところで、宮沢賢治は、地質学者とし
ての顔も持つことは、既によく知られている。Liparite(石英粗面岩)に愛着を持ち、ルートマップの記載は詳細を極めるという。童話「イギリス海岸」には、花巻市の北上川と猿ヶ石川との合流点近くをドーバーの白亜の崖に見立て、露出する第三紀の泥岩に偶蹄類の足跡化石まで見つけている様を描いている。

鹿踊り(詩歌の森公園にて)
これに限らず宮沢賢治の作品には、地質学はもちろん、火山、土壌、気象、農業にいたる広範な話題が揃い、彼が博覧博識の自然科学者であったことを示している。その中には、今の時代にも些かも色褪せしない話題もある。
彼の代表作のひとつである「グスコーブドリの伝記」の最後に近い一節では、火山技師グスコーブドリ27歳のとき、イーハトーブ地方は寒冷気候に見舞われる。クーボー大博士との会話は次のように続く。
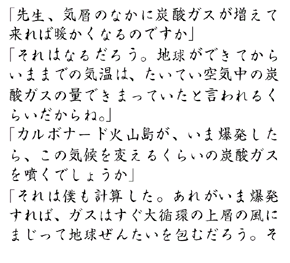
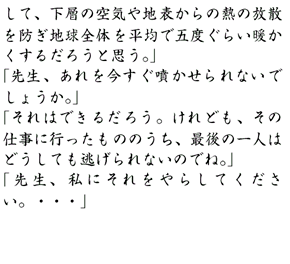
彼の視野は、一世紀も後の私たちの生きている世界を完全にその射程に入れている。この作品は全体として「自然の改造」にも近い彼の思想が色濃く現れているように見えるが、作品の評価は、当然のことながらそれを読む人によって違ってくる。
環境省の第5回環境基本問題懇談会(平成16年6月)の参考資料2「科学と環境年表」の“地球温暖化”の欄の1932年の項には、『宮沢賢治「グスコーブドリの伝記」でCO2増加による温暖化を書く』とある。
公平を期すならば、同欄の1896年(宮沢賢治の生まれた年!)の項に、『化学者アレニウスが石炭の燃焼によるCO2の排出が地球の温室効果を高め、温暖化を導くと提唱』ともある。
今日この頃は「地球温暖化」の言葉を見聞きしない日は無いといっても過言ではなく、世間一般も敏感になっている。
年表の編纂者の意図は推し量るしかないが、既に地の下に眠る賢治の迷惑そうな顔を思い浮かべてしまうのは、私だけだろうか。
宮沢賢治は、その作品にたびたび登場させる「イーハトーブ」について、生まれ育った岩手県をアンデルセン等の童話の世界に擬え、『心象中に、このような状景をもって実在したドリームランドとしての日本岩手県である。』(「『注文の多い料理店』新刊案内」より)と高らかに謳いあげた。彼は、緑深い北上山地や、豊かな水量の北上川を擁する岩手県は、必ずや理想郷になり得ると信じていたに違いない。
日頃市、奥火の土、薄衣、世田米、鬼丸、叶倉、鳶ガ森、唐梅館、坂本沢・・
その北上山地に抱かれたこれらの地名は、40年も前の学生時代に、北上古生層の標識地として、私の頭の中に入り込んだ。
とくに、東京育ちの私にとってエキゾチックでさえあった響きを持ついくつかの地名は、私をして一度は自分の足で歩き、自分の手でハンマーを振り下ろしたいと思わせた。
北上山地を指呼の間に臨むことができるようになった今、しかし私は未だに其処に踏み込むことをしていない。
億万年におよぶ地球の活動の痕跡を求めて山に分け入った先達の意気と、それを発見したときの感動を思いやると、既成の知識としてしか摂り入れることできない今の自分は、た易く彼らの足跡を辿ってそこに歩み入ることを躊躇してしまう。
そこは、風と、それに鳴る草木の葉摺れの音と、沢水の流れる音と、ひょっとすると木陰からじっと息を殺してこちらを窺う鹿の胸の鼓動まで聞こえそうな静寂の世界だったに違いない。その中で、彼らは、ひたすら古代のロマンを求めて歩き巡ったことだろう。
北上山地に聖地にも似た感情を抱いていた頃に登場した「プレートテクトニクス」(ただし、こんな洒落た言葉はまだできたばかり(1968年)で、私たちは知らなかった)を、浅学若輩の私たちは、その頃の人気テレビ番組から「ひょっこりひょうたん島」と揶揄した。
その頃の地質学の大勢は、日本列島が現在と同じ緯度経度の場所で、寒暖の気候変化を受けながら、隆起と沈降、浸食と堆積、大規模な褶曲と転位を繰り返してきたと、私たちに説明していた。
そんな私たちにとって、プレートテクトニクスは、大陸移動説の蒸し返しのような荒唐無稽なイメージでしかなかった。
今では、北上古生層も、実は遥か1万kmの南方から1億年の歳月をかけて、遥々この地にたどり着いたことは、当たり前のこととして地学の教科書に書かれている。
やはり宮沢賢治のいくつかの作品にモナドノック(残丘)の景色として登場する種山ヶ原高原は、北上山地の南西部に位置する。そこから北東へ約30kmの、同様にモナドノックである貞任山高原一帯には今、“ウィンドファーム”として、数10基の発電用風車が立ち並んでいる。青空と雲を背景に、風に向かってゆるゆると回る様は壮観ですらある。
北上山地が遥か南の海から長い旅をしてきたことを知り、その稜線に風車が立ち並ぶ今の景色を見ることがあれば、賢治や北上古生層を発見した先達は、いったいどんな感慨を抱くことだろうか。
(平成19年7月)