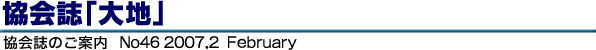|
仙台文学館 村上 佳子 |
 |
|---|
45.文学の中の食、その楽しみと味わい
前号でも紹介させていただいた仙台文学館の「藤沢周平の世界展」は、昨年秋、大好評のうちに終了いたしました。展示室はもとより館内のレストラン「杜の小径」も連日の賑わいで、開館以来の売り上げを記録したとのことです。ご来館くださった方々に心から感謝申し上げたい気持ちです。今回は、会期中にちょっと話題になりました食事にからめて、食べものをテーマにしてみたいと思います。
「海坂藩の食卓」と名づけられたランチは、藤沢周平のふるさとである山形県の庄内地方の食材を使って、店長が腕をふるったお膳です。いずれも素朴な家庭料理ですが、その味わいは展示とともに皆様に喜ばれました。
内容をご紹介すると・・・
<海坂藩の食卓(庄内の味わい)>
・棒ダラの煮物
(鱈を乾燥させて作られた棒ダラを長時間かけてやわらかく煮込んだ酒田の代表的な一品。伝統的な家庭料理の煮物は出来上がるまでに三日以上もかかり、期間中厨房のスタッフたちはこの臭いが身体から取れなかったという)
・むきそば
(酒田独特のごっつぉのひとつ。そばの実の歯ざわりを生かし、だしのきいたお汁と一緒にいただくすっきりとした味わい)
・米
(庄内地方で作られているこだわりのブランド米「はえぬき」を炊く。映画「蝉しぐれ」の黒土三男監督はJA全農庄内の庄内米ファンクラブ会長の名誉職にある)
・民田なすの漬物
(藤沢周平が生まれた集落の隣にある民田地区で作られる茄子の漬物。丸い小茄子が日々クール便で届けられた)
・みょうがの甘酢漬け
(素材のうま味をそのまま生かしたシンプルな漬物。店長得意の一品)
・いかとわかめの酢みそ和え
(酒田沖飛島の方面ではイカが多く水揚げされ、さまざまな料理で親しまれているとのこと)
・青菜のおひたし
(季節の青菜に食用菊「もってのほか」があしらわれた食欲をそそる一品)

「藤沢周平の世界展」限定メニュー海坂藩の食卓
藤沢作品に登場する食べ物といえば、「三津屋清左衛門残日録」の小料理屋の場面が良く知られており、藤沢周平を紹介する本の中にもしばしば取り上げられています。この作品は、藩の要職を退き隠居した清左衛門が、藩主や旧友たちからの信頼も篤いその人柄と見識によって、さまざまな事件の解決に力を貸しつつ、老いに向う自らの姿を見つめていく物語です。特に後半は馴染みの小料理屋「涌井」が、旧友の町奉行との密談といった大事な場面で使われ、二人の好物の肴が登場します。

『三津屋清左衛門残日録』(文春文庫)
肴はさっき言った小鯛の塩焼きで、ほかに豆腐のあんかけ、山菜のこごみの味噌和え、賽の目に切った生揚げを一緒に煮た筍の味噌汁、山ごぼうの味噌漬けなどが膳にのっている。
筍の味噌汁には、酒粕を使うのが土地の慣わしだった。(「立会い人」)
肴は鱒の焼き魚にはたはたの湯上げ、茸はしめじで、風呂吹き大根との取り合わせが絶妙だった。それに小皿に無造作に盛った茗荷の梅酢漬け。
「赤蕪もうまいが、この茗荷もうまいな」(中略)
はたはたは、田楽にして焼いて食べるのもうまいが、今夜のように大量に茹でて、大根おろしをそえた醤油味で喰べる喰べかたも珍重されている。町奉行は勢いよく、ぶりこと呼ばれるはたはたの卵を噛む音を立てた。浜では、はたはたがとれるようになると、季節は冬に入る。(「早春の光」)
主人公の清左衛門は妻に先立たれ、息子夫婦とともに暮らしています。良く気が利く申し分の無い嫁の里江は、舅が寝込んだときも手厚い看護をし、そこでも、病人を気遣う食事が出てきます。
里江が根気よく薬を煎じ、清左衛門の食欲が衰えたとみると、婢にはまかせずに自分の手で蕪の酢の物、小茄子の浅漬け金頭の味噌汁、梅干しをそえた白粥といったふうに献立に心を砕き、一箸でも多く喰わせようと工夫したせいか、しつこかった風邪もようやくぬけた。(「草いきれ」)
物語の終わり近くには、「つぎはみぞれが降るような寒い日に来て、熱い鱈汁で一杯やるか」と、旧友とうなずき合う場面も出てきますが、作者自身、鱈が好物であったようですで、エッセイの中にも「鱈のどんがら汁」の美味しさについて書かれているものがあります。また、藤沢周平の長女・遠藤展子さんの著書『藤沢周平 父の周辺』(文藝春秋)にも父が夕飯を作るとき、メニューはいつも「タラちり」であったと記されています。

『藤沢周平 父の周辺』(文藝春秋)
同書には、他にも食べ物にまつわるエピソードがあります。
昭和45年頃、藤沢周平は業界紙「日本加工食品新聞」の記者をしていました。妻に先立たれて幼い娘とともに暮らしていましたが、後の夫人となる女性とめぐり合った時期でもありました。デートはいつも会社の帰り道を歩くだけでしたが、ある日、ハムを一本持って喫茶店に現れ、その場で包丁を借りてハムを半分にし、彼女にわたしたとのこと。取材先かどこかで頂き、本当は全部あげたかったのでしょうが、家にはお腹を空かせた娘と老母が待っていますから、半分こと相成ったのでしょう。それぞれ半分ずつのハムを大事に抱えて帰ったとのことです。なんとも微笑ましく、また、時代を感じるエピソードで心に残っています。
館内のレストランでは、藤沢周平展以外でも、毎回、企画展にあわせてランチメニューが作られています。
向田邦子の手料理をレシピにした「思い出膳」は、人参のピリ煮が好評でした。高村光太郎・智恵子展では、光太郎の詩から「アトリエの二人」と名づけてクリームソースをあしらったチキンを中心とした洋食のメニューが出されました。
他にも、宮沢賢治展の「山猫膳」、林芙美子展の「放浪記セット」、山口県から取り寄せたな「(中原)中也ビール」など、その時ならではの味わいを楽しんでいただきました。
さて、仙台文学館この春の企画は、芥川龍之介の展示を予定しています。レストランのメニューは現在考案中とのことですが、食べ物の話題として、芥川の短編「芋粥」をご紹介してみたいと思います。
平安朝の頃、摂政藤原基経に仕える五位の下級侍がいました。この者は、背が低く赤鼻で、目じりが下がり頬がこけ、人並みはずれて風采のあがらない貧相な男で、仲間からも、子どもたちからもいつも馬鹿にされ、蔑まれていました。何の希望も無いかに見えるこの男の唯一の夢は、「芋粥を飽くまで飲んでみたい」というものでした。芋粥とは、山の芋を切り込んで甘葛の汁で煮たもののことで、当時は無常の美味とされていました。五位の侍がこの芋粥を口にできるのは、年に一度の来客の折くらいで、それも僅かに喉を通るばかりの少量でした。いつしかこの芋粥を飽きるほど飲むということが彼の一生を貫く欲望となっていました。
ある時この望みをかなえるという同輩に連れ出され、敦賀の国まで出向くことになります。五位の侍は、下人たちが掘り出してきた山芋で大量の芋粥が作られる様子をみているうちにしだいに食欲を失い、一斗の器に盛られた芋粥を前にしては口をつける前から満腹を感じてしまうのでした。
そして彼は、「芋粥を飽くまで飲みたい」との欲望を大事に持っていられた頃の、皆に愚弄され罵られている憐れむべき孤独な、しかし同時に、幸福な自分をなつかしくふりかえるのでした。
「鼻」「蜘蛛の糸」などとともに芥川の代表作として知られるこの作品には、人間の愚かしくも哀れで切ない姿が、つきはなしたようでどこか暖かく描かれているように思います。
芥川龍之介といえば、神経質で理知的な顔を思いうかべますが、今回の展示では、新婚の妻にちゃんづけで語りかけたり、すきっ歯を気にしつつも優しく微笑むような表情もご紹介いたします。
レストランの特製ランチとともにお楽しみいただければ嬉しく思います。