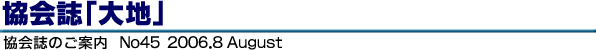|
仙台文学館 村上 佳子 |
 |
|---|
40.藤沢周平、その作品世界へのお誘い
仙台文学館の秋の特別展は「藤沢周平の世界展」です。前号のエッセイで映画をご紹介くださったロッキー鈴木氏は「重篤な藤沢病患者」とのことでございましたが、当文学館でも藤沢人気は高く、開館以来、最も待ち望まれていた展示です。平成9年1月、69歳で亡くなってから10年近くが過ぎた今も、その作品群は私たちの心をとらえ、広く読まれ続けています。
藤沢周平は昭和2年、山形県黄金村(現在の鶴岡市)の農家に生まれます。
六人兄弟の四番目、三男三女の二男でした。幼少時代をその地で過ごし、小学校では厳しい授業のため吃音となるといったエピソードもありますが、とにかく読書の楽しみをおぼえ、暇あればいつも本を読んでいたので、「ヒマアレバ」とのあだ名をもっていたそうです。
昭和17年から21年の戦中戦後の時期に、鶴岡中学校夜間部に学び、その後、山形師範学校に進学します。師範学校時代には、同人雑誌「砕氷船」に参加し、詩や評伝などを寄せており、すでに作家の片鱗をのぞかせていたのでしょうか。
しかし青年・藤沢周平は、その後、暗い時代を迎えることになります。昭和24年に師範学校を卒業、隣村の湯田川中学校に国語と社会の教師として赴任しますが、翌年父が死去、さらに翌26年には自身に肺結核が発見されます。
二十代半ばにして故郷を離れ東京で手術を受け、およそ6年にわたる療養生活を余儀なくされます。この間、俳句雑誌に参加したり、詩の会の同人に加わったりと、書くことで自己を表現することが続けられました。
やがて退院、その後も東京に留まり業界新聞の記者などを勤めながら小説に取り組みます。昭和34年には同郷の悦子夫人と結婚、2年後には長女も誕生し、また、「赤い夕日」が読売新聞の短編小説賞の選外佳作になり、新たな道をふみ出していきます。
しかし、その年の10月、幼い子を残して悦子夫人はガンによりこの世を去ることになります。藤沢周平はこのときを振り返り、その著作「半生の記」に以下のように記しています。
「胸の内にある人の世の不公平に対する憤怒、妻の命を救えなかった無念の気持は、どこかに吐き出さねばならないものだった。私は一番手近な懸賞小説に応募をはじめた。そしておそらくはそのことと年月による慰藉が、私を少しずつ立ち直らせて行ったに違いない」
昭和44年、和子夫人と再婚、46年には、「溟い海」によりオール読物新人賞を受賞します。その後発表した作品が数回にわたり直木賞の候補となり、昭和48年、「暗殺の年輪」で同賞の受賞にいたります。藤沢周平46歳の時でした。
「溟い海」は、江戸の絵師・葛飾北斎の晩年をとらえた市井小説。かつての栄光とうらはらに今は落目となってきた北斎が、近頃評判の若手絵師・広重に嫉妬のような敵意を募らせていく姿が、身持ちの悪い息子の話などとからませて緻密に描かれています。
「暗殺の年輪」は武家物の短編。父が藩内の政争により横死した過去を持つ葛西馨之介は、その事件の詳細が闇に包まれていることに加え、自分に対する周囲の憫笑の眼を感じていました。やがて、父の敵だった男に母が体を売ることで一家を破滅から救ったという真相を知り、馨之介は密かに敵の暗殺を決意します。

『暗殺の年輪』(文春文庫 2006年4月)
オール読物新人賞の「受賞のことば」には、40歳を超えての受賞について、作家の心境が述べられています。
「今度の応募は、多少追いつめられた気持があった。その気持の反動分だけ、喜びも深いものとなった。
ものを書く作業は孤独だが、そのうえ、どの程度のものを書いているか、自分で測り難いとき、孤独感はとりわけ深い」これらの受賞作をはじめ初期の作品群は、やはり暗い色調に満ちており、どこか作家の「追いつめられた気持ち」と通じるものを感じます。
作風に変化が現れるのは、昭和50年代に入り、「用心棒日月抄」シリーズを手がける頃からでしょうか。「暗い情念」から解き放たれたかのように、明るさとユーモアが加わり、生き生きした作中人物たちが読者の心をつかんでいきます。
名もない庶民の暮らしのなかの出来事をしみじみと描く「橋ものがたり」などの市井小説、「蝉しぐれ」「三屋清左衛門残日記」「たそがれ清兵衛」といった武家物語、さらに膨大な資料をひもといて描かれた歴史小説の数々も残されています。
絶筆となった作品「漆の実のみのる国」は、上杉鷹山を主人公とする歴史小説で、米沢藩の窮乏に立ち向かう若き藩主と、執政たちの姿が、読み進むのが苦しいほど淡々と描かれています。
名前ひとつをとりましても、市井人情物などでは、「おこう」「新兵衛」などと分かりやすいのですが、史実にもとづくこの歴史小説では、主人公の「鷹山」は号であり、幼名は「直丸」、やがて「治憲」となります。また、執政たちも、「竹俣美作当綱(たけのまたみまさくまさつな)」や「莅戸九郎兵衛善政(のぞきくろうべいよしまさ)」など読むだけでも骨が折れます。
鷹山は名君としての名が高く、不況が続く昨今は「鷹山にみるリーダー学?」といった実用書も多く出され、政治改革が思うに進まない現代の状況と重ねあわせて読むこともできます。
物語は、挫折につぐ挫折、漆や桑などの植樹政策の夢と現実、執政の罷免、自らの隠居?、困難を極める状況が最後まで続き、米沢藩が豊かに蘇った姿が描かることはなく終わります。
私は、「鷹山は名君なりか?」と改めて作者が問いかけるこの作品が妙に心に残り、特に次の一節には、一面ではとらえきれない人間の真実があるような気がしてなりません。
「大殿上杉重定は、小藩から養子に入って世子となり藩主となった治憲を、終始わが後継ぎとして礼をつくし、養子なるがゆえに隔てをおくような気配を一切示さなかった。これがひそかに乱舞狂いと謗られ、女子を愛し美食を好み、米沢一の浪費家、享楽家ともいうべき重定の半面だった。」
このたびの文学館の展示では、没後、ご家族のもとで大切に保管されてきた貴重な資料群により、藤沢文学の作品世界と作家の素顔をご紹介しています。
「蝉しぐれ」ヒロインの名前の候補が書かれたメモ、未完と思われていた「漆の実のみのる国」の完結部分の原稿、愛用の品々、近年発見された無名時代の作品掲載誌、そして書斎の再現など??是非、多くのお客さまにご覧頂き、藤沢ワールドの魅力にひたっていただきたいと願っております。
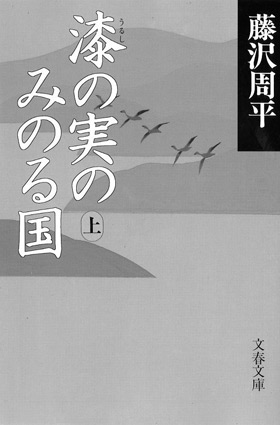
『漆に実のみのる国上』(文春文庫 2005年12月)