「戦争と平和」といえば、56年のオードリー・ヘップバーンのものを思い出す方も多いと思いますが、原作のイメージ通りなのは何といっても65年から67年にかけて3部作で公開された、旧ソ連版。合計7時間はギネス公認の最長映画ということです。雲の切れ間から俯瞰する大地のいたる所で「戦争」しているオープニングにまずビックリ。今の映画はCGでゴマかすから、絵としては可能かもしれないが、ソビエト赤軍数万のエキストラ出演による戦場シーンは、CG では表現不能な本物の生々しさが強烈でした。
ナターシャ役のリュドミラ・サヴェーリエワ(ハリウッド版に対抗し、ロシア全土からオードリーに似た娘を捜したといわれる)が16 歳のときに第1部を撮り、21歳になるのを待って第2部・第3部を撮ったという、旧ソ連でなければ不可能な「国作」映画。全体主義はゴメンですけど、ロシア民族の芸術に対する打ち込みようはとにかくスゴイ。さすがにハリウッドはこの映画にアカデミー外国語映画賞を与えています。
さて、近年わが山形県が舞台の映画が続々と公開されているのは、まことに目出たい限り。昨年は矢口史靖監督による「スウィング・ガールズ」という話題作なども発表されましたが、今年の話題は山田洋次監督「隠し剣 鬼の爪」と、黒土三男監督「蝉しぐれ」という、二つの藤沢周平作品が前後して公開されたことです。
何を隠そう、私は重篤な藤沢病患者。大方の例に漏れず、20代、30代くらいまでは藤沢作品の数倍、司馬遼太郎の小説を読み、天地を動かすようなスケールの大きな英雄列伝に没入していました。しかし人間40 歳ともなると、理不尽にも与えられた自らの境遇を見つめ、なお懸命に生きる藤沢作品の登場人物に、より惹かれるようになるものです。
その中でご存知「海坂藩」を舞台とした「蝉しぐれ」は、藤沢ファンすべてが認める、ジャンルを超えた大傑作。この作品は86年〜87年の山形新聞夕刊に発表されました。
黒土監督は、藤沢氏の生前に、本人から映画化の許可をもらった、日本一の藤沢ファン。ちなみに内野聖陽と水野真紀による、傑作の譽れ高いNHK ドラマ版「蝉しぐれ」は、黒土三男脚本によるもの。満を持しての映画化ということで、私の期待がいかに盛り上がっていたかも、想像していただけることと思います。
一方、「隠し剣」シリーズは、藤沢氏が『オール読物』に数多く連載した、海坂藩を舞台とした剣豪もの。大同小異のストーリー展開は、安心して楽しめる読物であるとともに、常にマンネリに陥る危険をはらんでいます。02 年に山田監督が映画化し、アカデミー外国語映画賞候補にもなった「たそがれ清兵衛」も、「隠し剣」シリーズとは違うけれどまったく同じ傾向の3 つの藤沢作品をミックスして作ってあり、藤沢のようで藤沢でない、でも藤沢らしい、というビミョーな映画でした。
私が藤沢周平をこれから読む人に何を読めばいいかと聞かれたとすれば、迷わず「蝉しぐれ」と答えます。そして密かに、他の「海坂藩」もの、例えば「隠し剣」シリーズを読まない方が、この美しい作品の印象が、より深く読む人の心に とどまるだろう、と考えます。
さて山田監督といえば、いうまでもなく「寅さん」です。「戦争と平和」が1話の長さのギネスなら、シリーズの長さのギネスが「寅さん」。マンネリを恐れ、乗り気ではないときもあったと聞きますが、営業サイドの要求から年2本のペースで「寅さん」全48作中46作を撮り続けた山田監督。「寅さん」から解放された山田さんが、「たそがれ清兵衛」に続き藤沢さんのもっとも職人的部分(商業作家として毎月書き続ける)を映像化するんかいな、しかもツギハギまでして、という気持ちは、正直ありました。
しかし、結論からいえば、山田監督はやはり邦画を代表する上手、名人、大職人でありました。藤沢作品である以上に山田作品、山田ワールドを体験しつつ藤沢テイストを感じ取る、といった具合で、映画と小説の違いをくっきりと際立たせながら、藤沢ファンをも納得させる職人ぶりでありました。山田ワールドを展開していくためには、「蝉しぐれ」のような完成された劇空間はかえって邪魔であり、小さなエピソードを膨らませて描くからこそ山田・藤沢の両巨匠の手管をふたつながらに堪能できるのだ、ということが、小説を読んだ人にはわかるのです。例えば登場人物が原作にはない庄内弁を使うなど、原作以上にリアリティを肉付けした部分もあり、十分に海坂藩の空気を伝えることに成功しています。もちろん、原作を読んでない人は、単純に山田時代劇として楽しめばいいわけです。
では、黒土監督「蝉しぐれ」はどうか。これは原作の可能な限り忠実な再現であり、藤沢ファンによる藤沢ファンのための映画、といっていいでしょう。せりふなども、原作をそのまま脚本に引き写したところがほとんどです。ファンとしては監督の映像化への執念に、拍手を送りたいところです。しかし、忠実な映画化だからこそ、映画としての制約からくる細かい変更が、かえって気になってしまう皮肉な結果にもなっています。
最大の問題は、キャスティングでしょう。染五郎の文四郎、木村佳乃のおふくは、それぞれ熱演ながらいささかトウのたった感じが惜しい。できれば、少年時代、青年時代をひとりの俳優が演じ(妻夫木聡とか)、中年時代を別の俳優が演じた方が、より強い印象を観客に与えられるのに、と思ったり(何しろ15〜20歳の青春期から当時としては初老である40 過ぎに飛ぶわけですから)。さらに、文四郎の二人の親友をふかわりょうと今田耕司が演じたのは、何か制作側に意図があったのだろうが成功していない。ぎこちなさもあるし、だいいち今田が出るたびに若い観客が失笑するので、興ざめになります。原作にはない、文四郎とふくを逃がすためにうつ臭い芝居も、なくてもよかったし。
文芸作品を原作に持つ映画は、上映時間という永遠にやっかいな問題があること、映画として冗長性を回避しなければならないことで、映画は常にストーリーの取捨選択を迫られます。この映画はそれは見事に「拾って」いますし、最後の逢瀬の場面など、原作にない光るせりふも効いています。しかし、え〜ここ捨てちゃったの〜というところが出てしまうのは、これはもう原作ものの宿命でしょうか。この点、細部を描けるテレビドラマの方が、原作を再現するのにはむいているのかもしれません。
原作では、父の死体を荷車で曵くとき、またクライマックスの決闘のとき、苦境の文四郎を助けるために危険や不利益を顧みずに駆けつける若者たちがおり、彼らはある意味では二人の親友以上に心強く、頼れる存在で、またそうした彼らに対する恩を決して忘れない文四郎の姿を描くことで、純朴な若者の群像を鮮やかに描いています。私の気分では、封建社会の閉塞状況の中で必死に支えあう彼らの姿に共感してこそ、ふくとのプラトニックな関係が胸に迫るんだと思います。ラストシーンの処理も、もっとも原作通りに描いてほしかった所です。
とはいえ、鶴岡市に保存されたオープンセットを見るまでもなく、原作の世界を手作りで再現しようとしたひたむきさが、この映画のエネルギーで、山田監督の職人芸にも、CG全盛のハリウッド映画にもない、この愛すべき映画の最大の魅力であることは、間違いありません。
この連載は今回で終了です。貴重な紙面に機会をいただき、編集部と購読者各位に感謝いたします。皆様のますますの活躍をご期待申し上げます。これからもみんなでいい映画をたくさん観ましょう!
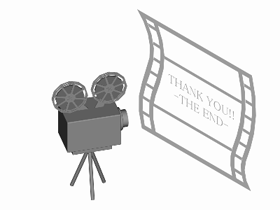
(イラストレーション:古川幸恵)
