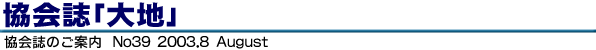武器よさらば
男の子というのはなぜか武器や兵器にひかれるもので、模型作りが最大の趣味だった中学時代の私も、随分たくさんの戦闘機や戦車を作ったものです。池袋パルコであった戦場ジオラマの大会に出かけたときなど、身分を隠したA 日新聞記者の取材に「兵器の持つ機能美は、戦争そのものとは別もので、戦争を肯定するつもりはさらさらない」という趣旨のことを、つたない言葉で答えたら、数日後の新聞に右傾化を危惧する記事が載り、その中で、軍国少年として登場していた、という少年時代最大の汚点を残しました。
湾岸戦争の頃から、茶の間で「テレビ観戦」していると、映画が現実を模倣しているのではなく実際の戦争のほうが戦争映画を模倣しているのでは、という錯覚に陥ります。
イラク戦争のさなかに開催された今年のアカデミー賞の会場では、ドキュメンタリー映画賞「ボウリング・フォー・コンバイン」のマイケル・ムーア監督の「ブッシュよ、恥じを知れ!」の雄叫びに喝采とブーングが半々に浴びせられ、また「戦場のピアニスト」で主演男優賞のエイドリアン・ブロディーの平和への祈りに共感の拍手が鳴り響き、まさに「戦時下のオスカー」の様相でした(もっとも正直、ブロディーがプレゼンテーターのニコール・キッドマンとかわした日本人の挨拶の感覚をはるかに超えた熱〜いキスには、もっと驚きましたけど)。昔から戦争映画というジャンルには、「西部の戦線異常なし」や「プラトーン」に代表される反戦のメッセージの強い映画があり、その一方では「史上最大の作戦や」「眼科の敵」のような戦争の持つスペクタクルやドラマ性を強調した娯楽映画があります。
しかし、これはどちらかに単純に色分けできるものでもなく、ほとんどの戦争映画が―戦意高揚の国策映画はともかく―両方の要素を持っているものですが、本音をいってしまえば見世物としての戦争がいかに魔力を持っているかは、最近の戦争報道の高視聴率にも表われています。
この場合、本物らしければらしいほど、満足度も高くなるわけで、東宝の「日本海大海戦」など、円谷プロの特撮でかなり見ごたえがありましたが、どこか「いわゆる特撮映画です」というモジモジ感があったような気がしました(余談ながら、誰もが映画化されないのを不思議に思っていた司馬遼太郎「坂の上の雲」が来年TV ドラマ化されるそうで、日本海大海戦のシーンがどこまで再現されるか注目です。司馬未亡人のコメントでは、故人はこの作品が戦争を賛美していると思われるのを嫌い、それがこれまで映像化されなかった理由だとのこと。本当は、明治天皇への殉死により美化されてきたが実は無能な乃木将軍に率いられ、おびただしい戦死者を出した旅順攻撃の実態を暴くなど、戦争の愚かしさを充分に描いた作品なのですが)。
そこへ行くと日米合作の「トラ・トラ・トラ!」や「ミッドウェー」はさすがに当時の邦画では不可能なすごい迫力でした(でも、パール・ハーバーを描いた前者はアメリカでは大コケ、ミッドウェー海戦を描いた後者は大ヒットでした、やっぱり。前者の日本の描き方は山本五十六役の山村聡以下珍しく自然で、逆に後者の山本五十六役三船敏郎以下は、いかにもハリウッド製のヘンテコ日本人役でしたけど。ああ、そういえばこないだのディズニー製戦争映画「パール・ハーバー」の無茶苦茶さもひどく、日本軍は野原で旗を立てて会議をしていました)。
比べるほうが無理かもしれませんが、かつてのソ連の官製映画、「ヨーロッパの解放」シリーズなど、戦争シーンを撮影しているのではなく、撮影のために戦争しているといった有様でしたし、逆に「プライベート・ライアン」など、現代のハリウッド製戦争映画は、CG などの映像技術を駆使して、驚くべきリアルさを表現しています(もっともこちらの技術では、日本も潜在的には高いものを持っているようです。でも、お金をかければキリがない世界ですから、その点が、ね)。
ちょうど「プライベート・ライアン」の頃から「シン・レッド・ライン」「U −571 」「スターリングラード」「ウインド・トーカーズ」などの佳作が次々封切られ、ハリウッドはちょっとした第2次世界大戦映画ブームの様相ですが、いずれもかつてのアメリカ=正義の味方という単純な構図のものではなくなってきてはいます。
また、「戦下の勇気」や「スリー・キングス」「ブラックホーク・ダウン」など、湾岸戦争以後のアメリカの軍事介入に題材を取ったものもありますが、作り手にとってまだまだ生々しいせいか、これらの戦争そのものの意味を問うたものはまだありません。そのうち、イラク戦争についての映画もできるのでしょうけどね。
すべての戦争映画は平和の反面教師、というのは戦闘シーン好きの男の子の言い訳めいてますが、例えば、真珠湾攻撃とは正反対にアメリカ人好みのテーマ、ノルマンディー上陸作戦をテーマにした前記両作(「史上最大の作戦」と「プライベート・ライアン」)の作者の視点を比較すれば、この50 年間の社会の市民化の進展ぶりが実感できます。しかし、「史上〜」のラスト近く、再激戦の上陸地点の指揮官役、ロバート・ミッチャム(前記「眼下の敵」でも主演、独軍指揮官役はともにクルト・ユンゲンス)がようやく付け直した葉巻の煙には、勇敢さへの称賛と同量の人間の業の苦しさが、表現されていたと思います。
さて、映画も現実も、主役ではなければ気がすまない?アメリカですが、先に亡くなったハリウッドの代表的二枚目スター、グレゴリ−・ペックが「アラバマ物語」で演じた差別と戦うフィンチ弁護士が、インディ・ジョーンズやジェームス・ポンドといった肉体派を抑えて、先ごろ堂々「映画史上のヒーローNO.1 」に選ばれました。これもかの国の多様性を示していると思いますが、そういえばペックの代表作のひとつ「大いなる西部」では、ハリウッド・ハト派の代名詞ペックと、銃所持放任論者の重鎮でタカ派俳優の代表、チャールトン・ヘストンの映画史上最長?の殴り合いがありました。まるでアカデミー受賞式を先取りしていたかのようですが、現実のほうは映画のように、ハト派主導の和解のシーンがラストに見られますかどうか。